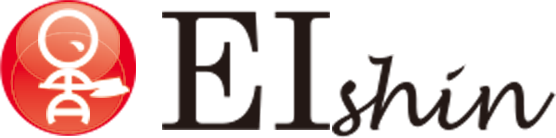「億ション」という言葉はもう古い?普通スペックの住戸も1億超えの時代に。

「億ション」という言葉はもう古い?普通スペックの住戸も1億超えの時代に。
今回は、1億円を超える高価格帯の「億ション」と呼ばれる新築マンションに注目し、特に億ションが集中する東京都心部(都心5区:千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区)の億ションの供給動向を調査した。
新築マンション価格が高騰しているが、特に都心部の高価格帯のマンションが価格の上昇をけん引しているといわれている。高価格帯の新築マンションの象徴といえるのが「億ション」と呼ばれる戸当たりの価格が1億円を超える新築マンションだ。
都心5区で供給される新築マンションのうち、億ションの供給推移を見ると、タワーマンションなど大規模なマンションが都心部で供給されることによる上下はあるものの、2017年以降はコンスタントに年間1,300戸前後供給されている。
2023年は2,645戸の供給があり、過去10年で最も億ションが供給された。エリア別にみると、最も多いのが港区、次いで渋谷区、中央区と続く。
湾岸エリアを擁す港区や中央区は規模の大きいタワーマンションが建てられるケースも多く、億ションの供給戸数を押し上げている。
一方で、千代田区や新宿区は、大規模マンションの供給自体が少ないことから、都心5区の中では億ションの供給が少ないエリアになっている。
各区の億ションの1m2あたりの価格の推移。約10年前、2013年時点では5区全体の平均が152万円/m2(約65m2で1憶円、100m2で約1憶5,000万円)だった価格が、2023年では296万円/m2(約33m2で1億円、100m2で約3憶円)に高騰している。
2023年は三田ガーデンヒルズ(平均409万円/m2)の影響もあるが、その他の区でも2013年と比べ1.4~1.8倍程度、中央区、新宿区を除き1m2あたり200万円超(50m2で1億円、100m2で2憶円)の相場になっている。
新築時に1億円未満で販売されていた住戸(供給の絶対数が多い)が昨今のマンション相場の高騰によって、1億円以上の値付けで販売されるケースが増えているためだ。都心湾岸部のタワーマンションなど人気のマンションでは、新築時の2倍近くの価格で流通するケースもみられている。
数年前までは、「億ション」と言えば、都心部にある豪華でハイグレードな仕様のマンションが中心だったが、昨今の新築マンション価格の上昇によって、そういったマンションはより高額になり、一般的な広さやグレードの住戸も「億ション」になるケースが増えてきた。超低金利が続き実際の住宅ローンの支払金額が抑えられているため「億ション」を購入できる層自体が増えていることも億ションが増えている要因の一つと考えられる。
地価や人件費、建築費などの高騰に伴い、マンション開発コストも上昇の一途を辿っている為、新築マンションが値下がりすることは考えにくい状況だ。
「億ション」が既に珍しいものでは無くなり、かなり身近なところまで近づいている今の状況が続くと、近い将来「億ション」がより一般的になり、「億ション」という言葉自体を使わなくなる時が来るかもしれない。
新築マンション価格が高騰しているが、特に都心部の高価格帯のマンションが価格の上昇をけん引しているといわれている。高価格帯の新築マンションの象徴といえるのが「億ション」と呼ばれる戸当たりの価格が1億円を超える新築マンションだ。
都心5区で供給される新築マンションのうち、億ションの供給推移を見ると、タワーマンションなど大規模なマンションが都心部で供給されることによる上下はあるものの、2017年以降はコンスタントに年間1,300戸前後供給されている。
2023年は2,645戸の供給があり、過去10年で最も億ションが供給された。エリア別にみると、最も多いのが港区、次いで渋谷区、中央区と続く。
湾岸エリアを擁す港区や中央区は規模の大きいタワーマンションが建てられるケースも多く、億ションの供給戸数を押し上げている。
一方で、千代田区や新宿区は、大規模マンションの供給自体が少ないことから、都心5区の中では億ションの供給が少ないエリアになっている。
各区の億ションの1m2あたりの価格の推移。約10年前、2013年時点では5区全体の平均が152万円/m2(約65m2で1憶円、100m2で約1憶5,000万円)だった価格が、2023年では296万円/m2(約33m2で1億円、100m2で約3憶円)に高騰している。
2023年は三田ガーデンヒルズ(平均409万円/m2)の影響もあるが、その他の区でも2013年と比べ1.4~1.8倍程度、中央区、新宿区を除き1m2あたり200万円超(50m2で1億円、100m2で2憶円)の相場になっている。
新築時に1億円未満で販売されていた住戸(供給の絶対数が多い)が昨今のマンション相場の高騰によって、1億円以上の値付けで販売されるケースが増えているためだ。都心湾岸部のタワーマンションなど人気のマンションでは、新築時の2倍近くの価格で流通するケースもみられている。
数年前までは、「億ション」と言えば、都心部にある豪華でハイグレードな仕様のマンションが中心だったが、昨今の新築マンション価格の上昇によって、そういったマンションはより高額になり、一般的な広さやグレードの住戸も「億ション」になるケースが増えてきた。超低金利が続き実際の住宅ローンの支払金額が抑えられているため「億ション」を購入できる層自体が増えていることも億ションが増えている要因の一つと考えられる。
地価や人件費、建築費などの高騰に伴い、マンション開発コストも上昇の一途を辿っている為、新築マンションが値下がりすることは考えにくい状況だ。
「億ション」が既に珍しいものでは無くなり、かなり身近なところまで近づいている今の状況が続くと、近い将来「億ション」がより一般的になり、「億ション」という言葉自体を使わなくなる時が来るかもしれない。